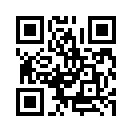2014年04月09日
漢詩の基礎やってみた(形式編)
王 翰(おう かん)作「涼州詩」を題材に
・葡 萄 美 酒 夜 光 杯
・欲 飲 琵 琶 馬 上 催
・醉 臥 沙 場 君 莫 笑
・古 來 征 戰 幾 人 回
「漢詩の基礎やってみた」に記載した「絶句と律詩」は「近体詩(きんたいし)」と言い、字数や句数、韻の踏み方など形式において定められた規則があります。
これに対して定まった形式がなく字数や句数、韻の踏み方が自由なものを「古体詩(こたいし)と言います。
ただ、近体詩が新しく、古体詩が古いということではありません。
近体詩の形式は唐の時代に確立されており、この時代以前のものを古体詩と呼びますが、唐の時代以降に作られたものでも形式に定められた詩になっていなければ古体詩ということになります。
「平 仄(ひょうそく)」の形式
漢詩には「声調」というものがあり、音程のようなものですが、漢詩ではこの声調を考えて詩を作ります。声調には「平声(ひょうしょう)」「上声(じょうしょう)」「去声(きょしょう)」「入声(にっしょう)」の4種類があり漢詩では「平声」を重視し、「上・去・入声」はまとめて「仄声(そくせい)」と呼び、ひと括りにします。これが「平(ひょう)」「仄(そく)」あわせて「平仄(ひょうそく)」です。
平仄(ひょうそく)の形式は「二六対、二四不同」と呼ばれ、「二六対」とは1句の中の2字目と6字目の平仄を同じにしなければならない決まりで、「二四不同」とは2字目と4字目の平仄が異ならねばならないという決まりです。例えば2字目が平声だったら4字目は仄声,6字めは平声にしなければならないといった感じです。
前後が「仄声」で挟まれた「平声」は避けてつくり、平声は必ず続いていなければなりません。
これを「孤平(こひょう)」と言い、1句の下3字に平声が3つ続くのも「下三平」といって避けなければならず、下3字では「平声」のみならず「仄声」の三連も避けて作るのが慣例となっています。
また、「平仄」には「粘綴(ねんてい)」という規則があり1句の2字目・4字目・6字目が「平・仄・平」であれば、2句は反対の「仄・平・仄」となる。つまりは奇数句から偶数句へ移るときは「平仄」を逆にしなければならない。だが偶数句から奇数句へ移るときは「平仄」は同じにする。よって2句が「仄・平・仄」ならば3句も「仄・平・仄」でなければならない。
形式の図解(□は平声、●は仄声、△は押韻)
葡□ 萄□ 美● 酒● 夜● 光□ 杯△
欲● 飲● 琵□ 琶□ 馬● 上● 催△
醉● 臥● 沙□ 場□ 君□ 莫● 笑●
古● 來□ 征□ 戰● 幾● 人□ 回△
この詩の「押韻」は一句末字の「杯」2句末字の「催」4句末字の「回」で「平声」である。
押韻が平声なので韻を踏んでいない3句末字「笑」は仄声である。「二六対・二四不同」の形式が守られ2句と3句の間に「粘綴(ねんてい)」が入り、また「孤平」も「下三平」もなく形式通りの詩になっている。
読み
葡萄 ぶどうの 美酒 びしゅ 夜光 やこうの 杯 はい
飲 のまんと 欲 ほっすれば 琵琶 びわ 馬上 ばじょうに 催 もよおす
酔 ようて 沙場 さじょうに 臥 ふす 君 きみ 笑 わらうこと 莫 なかれ
古来 こらい 征戦 せいせん 幾人 いくにんか 回 かえる
大意
葡萄酒を夜光杯で飲もうとしていると、馬上で琵琶をかき鳴らしてくれる者がいた。飲んで酔い潰れて砂漠に倒れ伏しても、君よ笑わないでくれ。昔からこの辺境に出征した兵士のうち、何人生きてかえれたというのか。出征した以上生きて帰れるかわからないのだから。
※このブログ(ページ)の内容は他人に教えようというものではありません。自分が独学で勉強していることを書き記して(ノート代わり)います。漢詩について詳しい方がおられたら、是非ご教示お願いいたします。
ここに記す事はすべて独学でやっており、誤った記載や解釈がある場合があります。
もし、間違いなどにお気づきの方はその旨コメントいただければ幸いです。
また、漢詩について詳しい方は是非ご教示いただけるようお願いいたします。
もし、間違いなどにお気づきの方はその旨コメントいただければ幸いです。
また、漢詩について詳しい方は是非ご教示いただけるようお願いいたします。
Posted by 肩書きだけは会長 at 20:25│Comments(0)
│漢詩